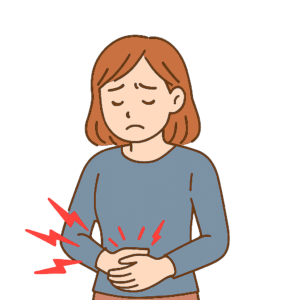最近、過敏性腸症候群で悩まれて来院される方が増えました。特に若い方に多く、外出先などで突然の便意や不安感で、トイレがあるかつい探してしまう。朝起きるとお腹が痛くて、一日のスタートが出遅れてしまう。など、皆さんに共通して、日常生活にまで支障が出てしまっています。過敏性腸症候群を知って、日常生活を取り戻しましょう。
過敏性腸症候群とは
過敏性腸症候群(Irritable Bowel Syndrome=IBS)は、腸にポリープや炎症などの消化器に問題がないにも関わらず、腹痛・便秘や下痢などの症状が長期間(1ヶ月以上)にわたり繰り返される症状のことをいいます。お腹が弱いと自覚がある方のほとんどは、過敏性腸症候群であることが多く、下痢や便秘、腹痛を繰り返すことで、日常生活に多大な支障をきたしています。ストレスや食事などによる腸内環境の乱れなどの要因が重なることで引き起こされ、検査では目立った原因が見つかりません。
よくある過敏性腸症候群のお悩み
腹痛や便調異常の繰り返しによる日常生活の制限
急な腹痛に見舞われ、予定通りにいかない、外出先や公共の場ですぐにトイレへ行けない状況での不安感や旅行やレジャーを十分に楽しめないなど、通常の日常生活が制限される場面が多くあります。
学業や仕事への支障
試験や会議、面接など重要な場面でトイレに行けない不安や、腹痛などで通勤や通学が困難になり、遅刻・早退・欠席が増えてしまうことがあります。
心的ストレスと精神的苦痛
症状への不安感が増すことでさらなるストレスとなり、さらに症状を悪化させるといった悪循環に陥ることがあります。また、学業や仕事への支障により、社会的に孤立感を感じてしまうこともあります。
過敏性腸症候群の特徴はなに?
主な症状としては、腹痛、下痢や便秘ですが、これだけではなく、お腹にガスが溜まって苦しくなったりすることもあります。これらの症状が1週間の内に1日以上でているかがポイントになります。自分の症状に当てはまるものがあるのかチェックしてみましょう。
☑下痢や便秘が長期間(1ヶ月以上)続いている
☑腹痛が繰り返し起こる(1週間に1日以上)
☑お腹に張りがある、または不快感があり苦しい
☑排便後も残便感があり、スッキリしない
☑便の状態が良くない(コロコロした便や水様便など)
過敏性腸症候群の種類があります
過敏性腸症候群と様々な種類があり、大きく4つに分けることができます。
1.下痢型
便秘型は、突然腹痛が起こるとともに下痢や軟便が出ます。便意をコントロールすることはできず、何度も腹痛や下痢・軟便を引き起こします。腹痛時には動悸がしたり、冷や汗が出たりするほどの痛みですが、排便すると症状がおさまります。特に男性によく見られます。
2.便秘型
便秘型は便が出にくく、お腹の張りや腹部の不快感を感じやすいです。3日以上便が出ないこともよくあり腹痛を伴いますが、便が出てもコロコロとした便しか出ず、出し切れていない残便感が残ることがあります。この型は女性に多く見られます。
3.混合型
混合型は、下痢と便秘が交互に繰り返され、腹部に不快感があります。症状もなかなか安定せず、排便もコロコロ便や水様便とどちらの便もあり、腹痛を伴います。男女ともに見られ、特に若年層で多く見られます。
4.分類不能型
下痢型や便秘型どちらにも分類しにくく、症状が変化します。下痢や便秘の症状よりも、お腹が張ったり、ゴロゴロと鳴る、ガスが溜まっているような感じがするなどの症状が多くみられます。
ストレスが過敏性腸症候群に与える影響とは?
過敏性腸症候群は、ストレスや不安を感じやすい人、感情表現の苦手な人、心配性な傾向のある人に、見られやすいです。
ストレスなどにより自律神経が乱れる
脳と腸は密接に関係しています。ストレスを感じると脳からホルモンが分泌され、自律神経が乱れます。
自律神経の乱れ
自律神経が乱れる事で、腸の運動が過剰となり下痢・便秘・腹痛などの症状が引き起こされます。
腸の過剰反応
腸が通常よりも過敏に反応し、わずかな変化や刺激に対しても痛みや不快感を感じやすくなります。
また、これらの症状が出たことにより、さらなるストレスや不安感が生じ、脳からホルモンを分泌させてしまい、悪循環が生じます。
過敏性腸症候群とサヨナラするには自律神経の改善が必須
過敏性腸症候群には、なにより規則正しい生活が大切になってきます。規則正しい生活を行うことで、自律神経の乱れをなくし、腸内の乱れも改善します。自律神経の乱れには、「睡眠」「食事」がポイントになります。
睡眠
夜になると副交感神経が優位になり、体を休息の状態にします。この間はなるべくリラックスして過ごすこと、7時間ほどの睡眠を確保するように心掛けましょう。起床時には交感神経が優位になります。しっかり陽の光を浴びることで、体内時計も整います。自律神経の乱れには、交感神経と副交感神経のバランスを保つことが大切になります。
食事
脂っこい食べ物や香辛料、カフェインやアルコールの摂りすぎ、過剰な食事摂取には気を付け、規則正しい食事時間や十分な水分の摂取を心がけます。また、アレルギーがある食べ物にも気を付けましょう。例えば、牛乳や乳製品など乳糖不耐症の人は下痢が誘発されます。このように食物によるアレルギーで腹痛や下痢が引き起こされることがあるので、それらには気を付けて食事を摂取しましょう。
当院での改善方法
「自律神経の調整」…交感神経が優位になると、腸に負担がかかり過敏性腸症候群の症状がでやすくなります。そのため、自律神経のバランスを整え、腸の負担を減らすことを目的とします。
「頭蓋骨の調整」…頭蓋骨から内臓に働きかけるホルモン分泌や神経伝達物質が分泌されています。頭蓋骨が緩むとホルモン分泌に異常を起こし、内臓機能の低下となるため、頭蓋骨を調整し、ホルモン分泌を正常にし内臓機能の低下を抑えるよう働きかけます。
「内臓の調整」…自律神経の乱れやホルモン分泌異常による、内臓の疲労を内臓の位置の調整をすることで、内臓の緊張状態を緩めます。
上記の3本柱で過敏性腸症候群の改善を目指します。
よくある質問
Q1. 保険は適用されますか?
A1. 整骨院での保険適用は捻挫、骨折、脱臼、打撲、挫傷のみが対象となり、かつ原因となる怪我をされてから2週間以内の急性のものに適用となっているため、過敏性腸症候群の施術ではお使いいただけません。
Q2. 薬を併用しながらでも施術は可能ですか?
A2. はい。可能です。お薬を併用しながらでも施術を受けていただけます。
さいごに
外出するたびにトイレが気になりトイレを探してしまう方、腹痛などにより学校に行けない方、突然の腹痛、便意で仕事に集中できない方、そんなお悩みを持つ方はぜひ当院にご相談ください。もともとお腹が弱いものだと諦めず、あなたの日常生活を取り戻しましょう。